- ホーム
- 研究について
- 研究者紹介 フロントランナー
- 009:稲見 昌彦 教授
009:稲見 昌彦 教授
稲見 昌彦 教授
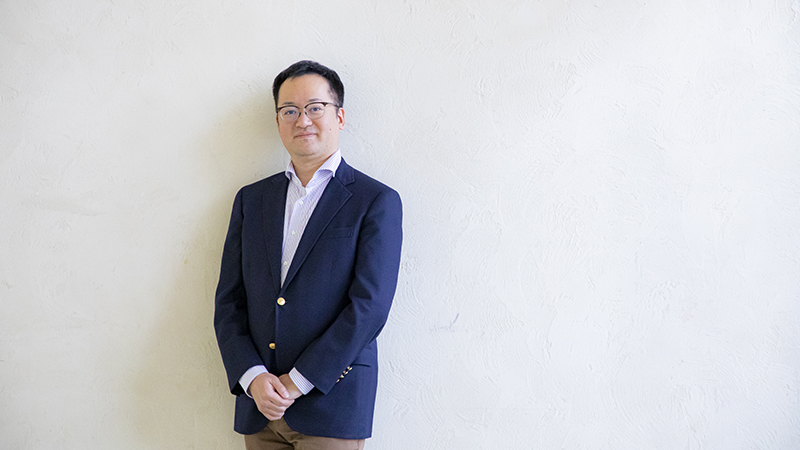
稲見 昌彦 教授
身体情報学 分野
公開日:2020年 2月25日
身体の「自在化」により、できることが増える社会へ――
「人機一体」の実現で進める人間拡張工学
生身の人間は、技術が加わることで変身するのだろうか。「分身」や「合体」はどうか。新たな自分の身体を人間はどのように知覚するのか。こうしたことを研究しているのが、身体情報学分野の稲見昌彦教授だ。身体に組み込まれた技術を意識することなく操る「人機一体」によって、「人間拡張」を実現し、身体を「自在化」させようとしている。
「透明人間」「超人」「サイボーグ」――。稲見教授の口から出てくる研究のキーワードはSFめいている。だがいずれのテーマに対しても、教授は真正面から真剣に向き合っている。
やりたい作業を心のままに実行する「自在化」
ここ数十年、社会では「自動化」が進み、工場での手作業をロボットが代替するようになった。洗濯も掃除などの家事でも機械が活躍している。「人間がやりたくない作業」を機械に担わせるという方向で、自動化は進んできた。
この機械による「自動化」と並立する概念として、稲見教授は「自在化」を提唱している。自在とは、心のままであること。「自在化」は、人間のやりたくない作業でなく、「人間がやりたい作業」を、機械やコンピュータを駆使して、より心のままにおこなえるようになることを指す。
「新しいものを創ったり、新しいことを体験したり、人間のやりたいことを時空や身体的制約を超えて実現させていくこともできる。それが自在化です」
自在化の身近な例として、稲見教授は文字入力時の「漢字変換」や「予測変換」を挙げる。たとえ漢字を覚えていなくとも、先まわりまでして漢字を示し、人間の「書きたい」を支援してくれる。
駒場リサーチキャンパスにある稲見教授の研究室にも、自在化のための技術の例がそこここで見られる。たとえば「Fusion」だ。操作者とロボット装着者の2人が遠くにいながらにして、ほぼ同一の視点から空間を共有し、ロボットアームで共同作業をすることができる。2人が「合体」することにより、共同作業という行為が自在化していく。
「自在化」を実現するため、さまざまな技術を駆使して人間本来の能力を飛躍的に高める研究がなされている。その技術や研究分野を、稲見教授は「人間拡張工学」と呼ぶ。
「人間拡張工学は、自在化を実現するための手法です。ロボット工学的な知識やバーチャルリアリティ、機械学習の知識も駆使します」
「人間拡張」を実現するうえで重要となる概念が「人機一体」だ。騎手が馬と一体化したかのように巧みに乗りこなすことは「人馬一体」という。このときの騎手は、馬をどう動かすか意識せずとも、意のままに馬が歩いており、それにより自分が動いているような感覚になっていることだろう。同様に、人間が機械と一体化したかのように無意識に機械を操っているときの状態が「人機一体」だ。
「なにもしないでも機械が身体の一部として動いてくれて、なにかしようとするときには意識的に身体を動かす。これがまさに人機一体が実現している状態です」
身体が「拡張」されたとき、人はどう感じるか
人機一体によって人間拡張が可能になり、人間拡張が自在化へとつながる。稲見教授は、この流れをイメージして研究を進めてきた。2008年からの慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科での研究などを経て、東京大学先端科学技術研究センター教授に2016年4月より就いた。
2017年10月より研究総括として主導しているのが、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業「ERATO」における「稲見自在化身体プロジェクト」だ。
稲見教授はプロジェクトの背景についてこう語る。
「人間と社会は常に共進化していくものです。今後、通常の五感では処理できないほど多くの情報が提示されたり、場所を超えて仕事をしたりということが増えていくと、身体ひとつではもたなくなります」
ERATOのプロジェクトにより、人間拡張の研究が加速している。成果のひとつが、「レビオポール(LevioPole)」というデバイスの開発だ。ポールの左右に付いている複数のプロペラの出力が個別に制御され、ポールを持っている人は、カヌーを漕いだり空を飛んだり、さまざまな触覚を得ることができる。VR(バーチャルリアリティ)やAR(拡張現実感)の技術と組み合わせることで、そこにいながらさまざまなバーチャル体験ができるほか、歩行ナビゲーションなどへの応用も考えられる。

加えて、稲見教授らが注力するのが、人間自体の理解だ。人間拡張や自在化がなされているとき、人間はどのような認知や行動をするのだろうか。脳神経の機能はどうなっているのだろうか。
こうしたことを探るための実験のひとつ、「ダイナミック・インビジブル・ボディ(Dynamic Invisible Body )」では、被験者のバーチャル身体が、手先・足先のみを残した「ほぼ透明人間」になっている。透明人間の自分に向けて突然、弓矢が飛んできたら被験者はどんな反応を示すのか。
)」では、被験者のバーチャル身体が、手先・足先のみを残した「ほぼ透明人間」になっている。透明人間の自分に向けて突然、弓矢が飛んできたら被験者はどんな反応を示すのか。
「実験では、身体が見えているときとほぼ同じように反応することがわかりました。たとえ透明であっても、人間はそこに自分の身体の存在を感じていることが理解できます」
ERATOのプロジェクトでは、一つの研究室が取り組む範囲を超え、早稲田大学、慶應義塾大学、豊橋技術科学大学、電気通信大学、それにフランス国立科学研究センターなどのメンバーと「叡智を結集して」(稲見教授)取り組んでいる。
「超人スポーツ」がもたらしたもの
稲見教授は、研究成果を伝えることにも重きを置く。学術界の人たちに理論で伝えるだけはでなく、一般の人たちに物語で伝えることの大切さも感じている。
「自在化や人間拡張に興味のない人にも物語を提供して『おもしろそうだからやってみたい』と感じていただければ、技術は広まるのではないかと考えています」
この戦略的な考えのもと、稲見教授は2013年より「超人スポーツ」を推進している。2015年6月には慶應義塾大学メディアデザイン研究科の中村伊知哉教授をはじめ、メディアアーティスト、デザイナー、アスリートたちとともに「一般社団法人 超人スポーツ協会」を設立した。「超人スポーツ」とは、人間拡張工学に基づき、人間の身体能力を「超える」こと、あるいは、年齢や障碍などの身体差により生じる人と人のバリアを「超える」ことを体現する運動競技のことだ。
「私もそうでしたが、運動に苦手意識がありスポーツ経験のない人が、老若男女や障碍の有無を超え、楽しくプレーできれば、テクノロジーのポジティブな部分を伝えることにもつながると考えました」
これまでに、22の競技が「超人スポーツ」に公式認定されている(2019年12月時点)。バネでできた西洋竹馬を足につけ、上半身は弾力性ある透明な球体を被って相手と格闘する「バブルジャンパー」や、体重移動のみで操縦できる電動バランスボードに乗り、オフェンス側がゴールにボールを入れていく「ホバークロス」などだ。
これらの競技はいずれも、協会が直接開発・提供したものでなく、公募して認定したものだ。公募形式にしたのは、今ある運動が得意な人たちだけでなく、競技開発やツール開発が得意な人たちにも参加してもらい、「スポーツクリエーション」の潮流も起こす狙いがあったからだ。スポーツも「つくる」ことができる。それを体感してもらおうと考えたのだ。
稲見教授はその好例として、「ロックハンドバトル」を挙げる。「2016年の『希望郷いわて国体』を機に、県知事から『超人スポーツを岩手でやりませんか』と、お話をいただきました。でも、東京で開発した競技で楽しんでくださいというのでは違和感がある。そこで地域の方々と“ご当地スポーツ”をつくることにしたのです」
その結果、岩手だからこその「ロックハンドバトル」が誕生した。盛岡市の三ツ石神社には、悪い鬼を懲らしめたとき、二度とこの地に現れないという約束のしるしとして、岩に手形を押したという伝説がある。それが「岩手」の地名の由来とされている。この伝説をモチーフに、「ロックハンド=岩手」で格闘するという競技ができあがっていった。

先端研はデパートではなくコンビニエンスストア
稲見教授の研究室には、博士課程・修士課程などの学生や、他大学・企業からの客員研究員を含め、総勢50名以上の研究メンバーがいる。
「身体に関わるおもしろいアイデアが出てきたら、まずはいったん試作機をつくってみる。いきなりメカにするのが難しければ、コンピュータの中で試作してみる場合もあります。それでうまく行きそうであれば、製造企業に製作を発注する。実機でアイデアを試すなかで、さらにうまく行けば何台かつくり、さまざまな研究者の方に使っていただいて、得られた知見を共有していきます」

「研究室には、プログラミングが得意な人もいれば、メカづくりが上手な人もいます。それぞれ自分の得意技を持ち寄って、“自分の居場所”を見つけてもらいながら取り組んでいます。人間拡張工学はまったく新しい領域なので、勉強してきたことはなんであれ、けっして無駄になることはありません」
修士課程の学生からも優れた成果が出ている。大伏仙泰さん(学際情報学府2年)は、指先搭載型の顕微鏡「マグニフィンガー(MagniFinger)」を開発した。指で触れたところを拡大して見られるのと同時に、表面の質感を指先で感じることもできる。

人間拡張工学は、大学だけでなく、民間企業も注目している分野だ。人間拡張をこれからの提供価値にしようとしている企業も見られる。そうした状況において、大学がこの分野の研究をする意義は何だろうか。稲見教授いわく、「意義は大きく二つある」とのことだ。
「一つは、解き方がわからない問題や、何が問題かさえわからない問題にも大学はチャレンジできるという点です。小規模の企業だと、製品やサービスとして利益を上げられるようになる前にあっという間に資金が尽きてしまいます。企業は、定義された問題の解き方を考えていくの対し、大学は、問題そのものを定義したり、領域を新たに創出したりすることにも取り組めます。ここに大きな違いがあると考えています」
「もう一つは、大学はハブの機能を担えるという点です。大学はある意味、社会で中立的な立場にあるので、業界の壁を超えて多分野の方とお付き合いすることができます。私たちが共同研究をしていた建設機器メーカーが抱いている問題意識が、同じく共同研究していたゲーム企業の問題意識と近いことがわかり、そのときの知見を生かせたこともあります」
大学は、それぞれに専攻をもつ研究者たちが同居するフラットな場でもある。なかでも先端研は、研究者どうしの交流から共創が生まれやすい場だと稲見教授は実感している。
「先端研は、東大にさまざまある部局にも所属している研究者の集まりです。私も、先端研だけでなく、情報理工学系研究科や情報学環の教授でもあります。そうした研究者たちが、定例教授会のほか、ハッピーアワー、教授会セミナー、カフェセミナーといったさまざまなイベントで顔を合わせ、気軽に相談しあったり、意見交換したりしています。本郷キャンパスがフロアごとに店舗の異なるデパートだとすると、先端研はふらっと新しいものがないかを見てまわれるコンビニエンスストアのような存在です」
新たな技術を生み出す研究者としての責任
稲見教授は高校時代、すでに「サイボーグのようなものをつくりたい」と考えていた。「サイボーグ」は、1960年、マンフレッド・クラインズとネイサン・クラインという二人の研究者が、宇宙環境における人間の身体のあり方を述べた論文「サイボーグと宇宙」で初めて使った言葉だ。現在は、「意識的に働かさなくても、完全に身体と一体化して動作してくれるような機械と生体との結合体」といった意味があたえられている。稲見教授の提唱する「人機一体」「人間拡張」「自在化」ときわめて近い概念といえよう。
こうした新たな技術に積極的な人もいれば、消極的な人もいる。人間のリスク認知の要素には、得体の知れないものにリスクを感じやすいという未知性因子があるとされる。「超人スポーツ」などで、新たな技術に楽しみを感じる人が増えてきている一方、依然として未知なるものに警戒感を抱く人たちがいるのも事実だ。
「もちろん社会的に受容されることは必要です。その点でいえば、少子高齢化が進む日本で、一人一人をエンパワーしていくニーズが後押しになることはまちがいありません。課題先進国として技術を確立しておけば、輸出産業にすることもできると思います」

その一方で、新たな技術の普及にともなう「ネガティブな影響」に対しても、研究者として責任をもって考慮しておかなければならないと言う。
「どういう悪影響がありうるかを調査して把握し、できればその悪影響が出た場合の処方箋も見出しておくべきです。新たな技術を使うことで、後戻りできなくなるかもしれない。そうしたことも含めて課題を洗い出し、対策や規制を考える必要があります。それをせず、ただ社会での成り行きに任せるというのは研究者として無責任なことです」
新たな技術は、社会のなかでときに難を生み出しながら、それを上まわる幸福をもたらしながら前に進み、広まっていく。
「人間は、できなかったことができるようになったことに、本質的なよろこびを感じるようにできています。昨日より今日、できなくなることが増えれば、老いや衰えを感じる。反対に、今日より明日できることが増えると感じられたとき、人間は未来に希望を抱くのではないでしょうか。新たな技術で、新たな体験をするということには、そうした意義があるのだと考えています」

1999年、東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻博士後期課程修了、博士(工学)。東京大学国際・産学共同研究センターリサーチアソシエイト、大学院情報理工学系研究科助手、電気通信大学電気通信学部講師、助教授、教授、マサチューセッツ工科大学コンピュータ科学人工知能研究所客員科学者などを経て、2008年、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授。2015年、東京大学大学院情報理工学系研究科教授。2016年より現職。2018年より東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター応用展開部門長を兼務。
関連タグ

